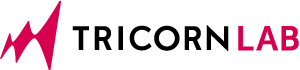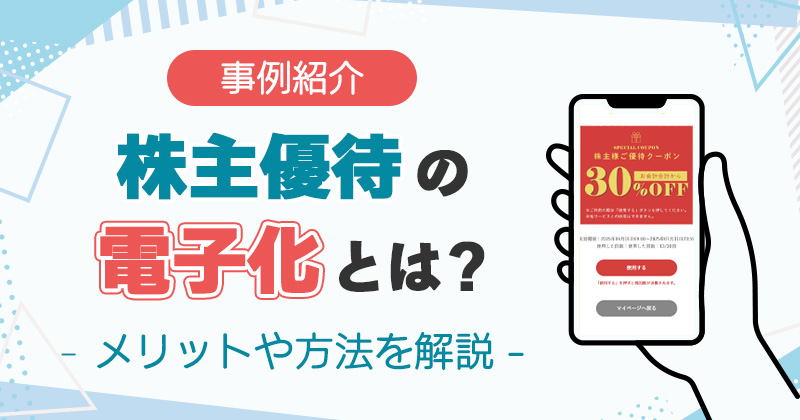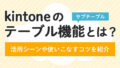株主優待の導入企業数が増えるなか、近年では株主優待の電子化が注目されています。
2024年1月には新NISA(少額投資非課税制度)が始まったことで、投資に関心をもつ層が広がりました。それに伴い、多くの上場企業が株主優待を拡充しており、2024年末時点の導入企業は1,500社を超えています。
大きな変化としては、紙媒体からの脱却も見逃せません。スマートフォンで表示できる優待券や、マイページから選べるカタログギフトなど、多くの企業が株主優待の電子化を進める時代になりました。
本記事では、株主優待を電子化するメリットや注意点に加えて、実際の方法を事例つきでご紹介します。
株主優待の電子化とは?

株主優待の電子化とは、専用のウェブサイトやアプリ、電子クーポンなどを用いて株主優待を提供することです。企業と株主の双方にメリットがあるため、近年ではさまざまな業界で導入が進んでいます。
| 企業側のメリット | 株主側のメリット |
|---|---|
|
|
これまで使われていた紙の優待券には、紛失や転売のリスク、郵送の手間といった課題がありました。その点、電子優待はウェブ上で提供・管理ができるため、不正利用を防ぎたい企業やスマホユーザーから好まれやすい特徴があります。
電子化が進んでいる背景
株主優待の電子化が進む背景には、以下のようなビジネス環境の変化があります。
- スマートフォンなどの普及率が上がり、より手軽なサービスが求められるようになった
- 物価の高騰により、コスト削減(紙代や郵送代など)の重要性が上がった
- 環境意識の高まりを受けて、紙媒体の廃止が注目されるようになった
- デジタル技術の進歩により、株主優待電子化のハードルが下がった
また、2024年1月から始まった新NISAも、株主優待の電子化が進む要因と考えられます。
個人投資家が増えやすい環境になると、上場企業は株主を増やすための施策に力を入れます。そのひとつが株主優待の拡充(実施や利便性の向上)であり、2024年には株主優待の導入企業数が廃止企業数を上回りました。
年が明けてからもこの動きは続いており、2025年には株主優待の導入企業数が過去最高になる見通しです(※2025年9月現在の予測)。
電子優待と紙媒体の違い
電子化した株主優待(以下、電子優待)は、紙媒体が抱えていた多くの課題を解決してくれます。具体的になにが変わるのか、ここでは電子優待と紙媒体の違いをまとめました。
| 項目 | 紙の株主優待 | 電子優待 |
|---|---|---|
| 受け取り方法 | 郵送 (届くまでに時間がかかる) |
専用サイトやアプリなど (すぐに受け取れる) |
| 管理のしやすさ | 紛失や破損、期限切れのリスクあり | スマートフォンなどで一元管理できる |
| 使い方 | 店舗に持参して提示が必要 | QRコードや電子クーポンの提示 |
| 企業側のコスト | 印刷代や郵送費がかかる | システムの開発費がかかる一方、 運用コストは削減できる |
| セキュリティ | 転売や偽造のリスクあり | 不正利用防止策を実装できる |
| 環境面 | 紙やインクを消費する | ペーパーレスで環境負荷が小さい |
上記のように比較すると、株主優待の電子化は運用コストを減らしたい企業や、株主の満足度を高めたい企業に向いていることがわかります。
株主優待を電子化するメリット(企業側)
企業が株主優待を電子化するメリットは、次の5つです。
- 1.業務効率化やミス削減につながる
- 2.コストを削減できる
- 3.株主のデータをマーケティングに活かせる
- 4.セキュリティの強化につながる
- 5.別の投資家層にアプローチできる
実際にどのような効果を期待できるのか、以下で詳しく解説します。
1.業務効率化やミス削減につながる
株主優待を電子化すると、発送先を入力するなどの手作業が減るため、業務効率化とミスの削減を実現できます。以下では、電子化によってカットできる主な業務をまとめました。
- 優待券などの印刷作業
- 発送に伴う宛名ラベルの印刷や封入、処理
- 保管や在庫管理
- 再発行への対応
- 使用された優待券の回収や利用状況の確認 など
電子化された株主優待は、システムを操作するだけですぐに提供できます。対応の遅れが生じにくいため、株主の満足度を上げることにもつながります。
2.コストを削減できる
紙媒体が不要になると、印刷費用や郵送費用、封入作業にかかる人件費などを削減できます。再発行の手続きもスムーズになるため、株主優待の電子化はコストカットにもつながる施策です。
どれくらいのコストカットを実現できるのか、以下では簡単なモデルケースを挙げてみました。
株主1人あたりにかかる費用を以下のように設定し、削減できるコストを計算してみます。
- 印刷費用:100円
- 封筒代:50円
- 郵送費用:84円
- 対象の株主:1万人
- 再発行の申請:500人(費用は初期の発送時と同じ)
(各費用の合計×対象の株主)+(再発行費用×申請数)=株主優待の実施費用
(234円×1万人)+(234円×500人)=245万7,000円
※実際の作業では人件費も発生するため、電子化によるコスト削減効果はさらに大きくなることが予想されます。
一方で株主優待を電子化すると、印刷費用や封筒代などはかかりません。初期費用やシステムコストは発生しますが、株主数が増えてもほぼ同じプロセスで株主優待を実施できるため、長期的なトータルコストを抑えやすくなります。
3.株主のデータをマーケティングに活かせる
株主優待を電子化すると、システム上に株主の属性情報が蓄積されます。たとえば、性別や年齢、お住まいの地域、趣味嗜好などがデータ化されるため、個々のターゲットに合わせた販促活動が可能になります。
- イベント会場から近い株主に、開催情報を知らせる
- 特定の株主層(30代や女性など)に向けて、おすすめ商品を訴求する
- ターゲットから選ばれやすい優待品を確認し、商品開発の方向性を模索する
株主は企業のオーナーであると同時に、自社製品に関心を示しやすいユーザーでもあります。接点を持つことで、貴重な口コミや意見を収集できることもあるため、企業にとって株主のデータは大きな財産になります。
4.セキュリティの強化につながる
株主優待の電子化には、偽造などの不正利用を防ぐ効果もあります。
2017年には、大手航空会社の社員が使用済みの優待券を転売した事件が起こりました。また、偽物の優待券がフリマサイトに出回るような事件も後を絶ちません。
その点、電子化された優待券は再利用や偽造が難しいため、紙媒体で起こりがちなトラブルを回避できます。株主優待のセキュリティを強化すると、不正利用による損害を防ぐことに加えて、会社の信用性アップにもつながります。
5.別の投資家層にアプローチできる
電子化によって株主優待の利便性が上がると、投資対象としての価値が高まります。既存の株主以外にもアプローチしやすくなるため、新NISAで投資を始めた若年層や海外投資家まで引きこめるかもしれません。
また、紙媒体の廃止はペーパーレス化につながるため、SDGsやESG経営(※)の観点でも貢献することが予想されます。
※持続可能性が注目される現代では、環境に関わる非財務情報も投資の判断材料になることがある。なかでもSDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)への貢献度は、多くの投資家が注目している指標。
参考:日本証券業協会「SDGs・ESGのいろは~証券投資でより良い世界を~|証券業界のSDGs」
当社が提供している、高セキュリティなCRMプラットフォーム「クライゼル」を利用して株主優待券の電子化が可能です。ぜひ、株主優待券のWeb化 | CRM・顧客管理システム「クライゼル」 をご覧ください。
株主優待を電子化するメリット(株主側)
株主優待の電子化にはさまざまな方法があるため、株主側のメリットも理解したうえで計画を立てることが重要です。主なメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 1.スマートフォンだけで管理できる
- 2.紛失や期限切れを防ぎやすい
- 3.特典の選択肢が増える
ここからは各メリットの詳細や、企業が押さえたいポイントを解説します。
1.スマートフォンだけで管理できる
電子化した優待品は、紙媒体と違って持ち歩く必要がありません。たとえば、店頭でQRコードを提示する仕組みにすれば、株主はスマートフォンだけで優待品を使用・管理できます。
スマートフォンでの管理がどのように役立つのか、以下ではわかりやすい例をまとめました。
- 店舗を見つけたときに、クーポンなどをすぐに提示できる
- 使用可能な店舗をすぐに調べて、マップ(アプリ)で場所も特定できる
- 現金と割引券などを併用し、端数がでないように会計する
株主の満足度を高めるには、手軽に優待品を使える仕組みにすることが重要です。株主が「どのシーンで使うのか」「どういった手順で使用するのか」をイメージしながら、株主優待の内容や仕様を決めましょう。
2.紛失や期限切れを防ぎやすい
電子化された優待品には、紛失や破損のリスクがほとんどありません。ログイン後のマイページから使える仕組みにすれば、仮にスマートフォンを失くしても別の機器で優待品を使えます。
また、受け取りまでに時間がかからない点も、電子化された優待品の魅力です。郵送の待ち時間が発生せず、かつ有効期限などをウェブ上で確認できるため、期限切れも防ぎやすくなります。
3.特典の選択肢が増える
株主優待の電子化が進むと、企業は紙媒体や自社製品に限らず、さまざまな優待品を提供できるようになります。たとえば、デジタルギフトやポイント付与に対応できるため、株主側の選択肢も広がります。
従来の株主優待では、「東京でしか優待券を使えない」といった地域格差も課題でした。一方、電子優待はオンラインショップなどとの連携がしやすいため、どの地域でも平等に優待を受けられる可能性が高まります。
株主優待を電子化した事例
株主優待の電子化は、株主や投資家のニーズを軸に進めることが重要です。以下の図では、実際に電子化を進めている事例を参考にして、具体的な方法や導入効果をまとめました。

電子化によって提供できる優待品は、導入するシステムによって異なります。ここからは、当社のCRMプラットフォーム「クライゼル」を例にして、電子優待のわかりやすい事例をご紹介します。
事例1.優待品を選択できるフォームの実装
ひとつ目は、株主優待の申請用フォームを作成した事例です。株主による入力内容がデータベースに自動蓄積されるため、郵送作業などの効率化を図れます。
配送先情報に加えて優待品の選択項目を作っておけば、往復はがきでのやり取りも必要ありません。各株主に1通のメールを送るだけで、株主優待の案内を済ませられます。

配送先情報のほか、配送希望時間帯の項目を作ることもできます。
セキュリティを高めたい場合は、株主番号をID、郵便番号などをパスワードとして、株主用のログインページを作ることも可能です。

ログイン情報は自由に設定できるため、電話番号をパスワードにすることも可能です。
実際のフォームを確認したい方は、こちらのデモページをご覧ください。
事例2.優待用マイページで電子クーポンを発行
株主用のマイページを作成し、ウェブ上で電子クーポンを発行する方法もあります。
たとえば以下の画像は、スマートフォン用のクーポンをマイページ上で表示した事例です。当社にご相談いただいた外食事業会社様が導入されたシステムで、使用回数が自動でカウントされる仕組みになっています。

実際の使用時に回数が自動でカウントされます(上図の青枠)。
マイページを「500株以上」「1,000株以上」のように分けると、持ち株数に応じた優待品を設定することも可能です。さらに、マイページ上にイベント情報を掲載するなど、株主とのコミュニケーションやマーケティングにも役立ちます。
実際のデザインや操作感を確認したい方は、こちらのデモページをご参照ください。
事例3.通知はがきにQRコードを掲載
株主総会決議通知や配当金通知に、電子クーポンのQRコードを掲載する方法もよく見られる事例です。シンプルな仕組みですが、専門的なコーディングやウェブデザインが不要なため、スムーズに株主優待の電子化を進められます。
ここまでご紹介した優待システムは、いずれも当社のクライゼルで実装できます。クライゼルには、顧客関係管理(CRM)に役立つさまざまな機能が備わっているため、株主優待の電子化と同時にマーケティングを強化したい企業者様におすすめです。
- 申請用のフォームやマイページの作成(フルコーディング可能)
- 電子クーポンやQRコードの発行
- フォームに入力されたデータの保管
- 一斉メールやメルマガの配信
- クーポン利用状況のグラフ化
クライゼルの活用方法については、下記のページで詳しくご紹介しています。
株主優待を電子化するときの注意点
株主優待の電子化には、以下のようなデメリットもあります。
- 情報漏えいやサイバー攻撃などのリスクがある
- 電子優待を使いこなせないと利便性が下がる
- システム障害時の被害が大きくなりやすい
- 初期費用(システム導入費)が高額になることもある
上記のデメリットを抑えるには、実際の運用をイメージしながらシステム設計をすることが重要です。ここからは、株主優待の電子化で意識したい注意点をご紹介します。
高度なセキュリティ設計にもこだわる
魅力的な優待品を用意しても、サイバー攻撃などで株主の個人情報が漏えいすると、会社の信用性は大きく低下します。多くの投資家から株主優待を利用してもらうには、セキュリティにもこだわって利便性と安全性を両立することが必要です。
参考として、以下では重要度が高いセキュリティ要件をまとめました。
- SSL(暗号化通信)
- テキスト項目の暗号化
- 二段階認証
- 自動ログアウト機能
- システムの権限設定やIPアドレス制御
- 侵入検知システム
外部サービスを利用する場合は、提供会社のセキュリティ体制を確認することも重要です。クライゼルを提供するトライコーンは、システム面でのセキュリティ強化に加えて、PマークやISO/IEC27001、ISO/IEC27017規格を取得しており、組織面でのセキュリティ強化も推進しています。
紙媒体を好むアナログ世代にも配慮する
スマートフォンを使い慣れていない世代は、QRコードや電子クーポンを敬遠しがちです。株主優待の電子化を安易に進めると、デジタルを苦手とする高齢株主などが離れてしまうかもしれません。
紙媒体を好むアナログ世代にも配慮する必要があるため、以下の施策にも取り組みましょう。
- 紙媒体の優待品も残しておく
- チュートリアルや操作ガイドを充実させる
- サポート窓口(電話での説明)を用意する
上記のほか、電子優待の利便性を高めることも重要なポイントです。電子クーポンを例にすると、「複数枚をまとめて使えるか」や「少額使用でも無駄にならないか」などの違いで、株主からの印象は変わります。
電子化だけでは利便性向上につながらない場合もあるため、優待内容やシステム設計は慎重に検討してください。
障害を想定したシステム設計にする
デジタル技術を活用する場合、ネットワークやシステムの障害は避けられません。トラブルのタイミングも予測できないため、障害を前提にしたシステム設計が必要です。
たとえば、クライゼルでは24時間のサーバ監視を行うことで、システムエラーへの早急な対処を実現しています。そのほか、トラブル時に稼働するバックアップシステムや、サポート窓口の整備も有効な対策です。
株主優待を電子化する方法
株主優待を電子化する方法は、「システムの自社開発」と「外部サービスの活用」に大きく分けられます。ここからは、各方法のプロセスやメリット・デメリットを解説します。
システムを自社開発する
株主用のウェブサイトやフォーム、情報管理用のデータベースなどを独自に開発する方法です。主にアプリで電子化を進めたい企業や、別のシステムと連携(会員サイトなど)させたい企業に向いています。
自社開発をするメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| 自社開発のメリット | 自社開発のデメリット |
| ・自由度が高いシステムを構築できる ・別のシステムと連携しやすい ・株主のデータや利用ログを直接管理できる | ・開発コストや運用コストが高くなりやすい ・開発に時間がかかり、高度な人材も必要 ・セキュリティ機能も実装する必要がある |
自社開発は自由度が高い一方で、システムの設計・開発に手間がかかります。開発後にはテスト運用をし、フィードバックを踏まえて修正する必要もあるため、低コストやスピードが求められるシーンには向きません。
基本的にはシステムの要件定義を行い、外部サービスでの実装が難しいとわかった時点で、自社開発を検討することが望ましいでしょう。
外部サービスを活用する
電子優待に対応した外部サービスを導入し、月額料金を払いながらシステムを運用する方法です。例としては当社のクライゼルや、デジタルギフトに対応した「デジコ(DIGITALIO社)」、優待券をデジタル化できる「選べるe-GIFT(全日空商事社)」などがあります。
自社開発に比べると開発の手間を省けるため、短期間でシステムを実装したい企業や、開発コストを抑えたい企業に向いています。
| 外部サービスのメリット | 外部サービスのデメリット |
| ・開発の手間やコストを抑えやすい ・セキュリティ機能も備わっていることが多い ・法改正にも対応しやすい | ・ランニングコスト(月額料金)がかかる ・カスタマイズに限界がある ・サービスによっては外部連携が制限される |
外部サービスを利用する場合も、システムの要件定義が欠かせません。サービスによって機能やカスタマイズ性が異なるため、「このサービスで実装できるのか」「株主が使いやすいか」については慎重な判断が必要です。
クライゼルを活用する
クライゼルで株主優待を電子化する場合は、以下のプロセスが必要になります。
- データベースを設定する
- 作成したデータベース上に、フォームまたはサイトを設定する
- ログイン用のページを作成する
- フォーム・サイト用ページのコーディングをする
- 株主情報をアップロードする
クライゼルでは、作成したデータベース上にフォーム・サイトを作成します。マイページなどで株主が入力した内容は、レコードとして自動蓄積される仕組みなので、外部のデータベースと連携させる必要はありません。

株主用マイページにフォームを設置した場合も同様です。
電子クーポンを実装する場合は、データベース上にサイトを作成し、ページ作成のボタンから「アタッチメントページを作成する」を選びます。ページ名称などを入力して次に進むと、「見せるクーポン」または「押せるクーポン」の選択画面が表示され、クーポンの設定が可能です。

「使用する」のボタンを設置したい場合は、押せるクーポンを選択します。
クライゼルのサイト作成は、フルコーディングに対応しています。HTMLコードの入力により、ログインページやマイページ、クーポンの使用ページなどを自由にカスタマイズできます。
コーディングが不安な方に向けては、わかりやすいマニュアルやサポート窓口もご用意しています。また、クライゼルを使った株主優待システム自体の制作代行も承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
株主に配慮した電子優待を目指そう
株主優待の電子化は、企業と株主の双方にメリットがある施策です。すでに多くの企業が取り組んでいるため、導入が遅れると投資家の関心が薄れるかもしれません。
電子化を進めるうえでは、ひとり一人の株主に配慮し、誰もが安全に利用できる方法を模索することがポイントです。本記事を参考にしながら、優待内容やシステム設計を考えてみましょう。