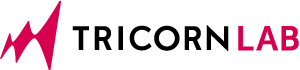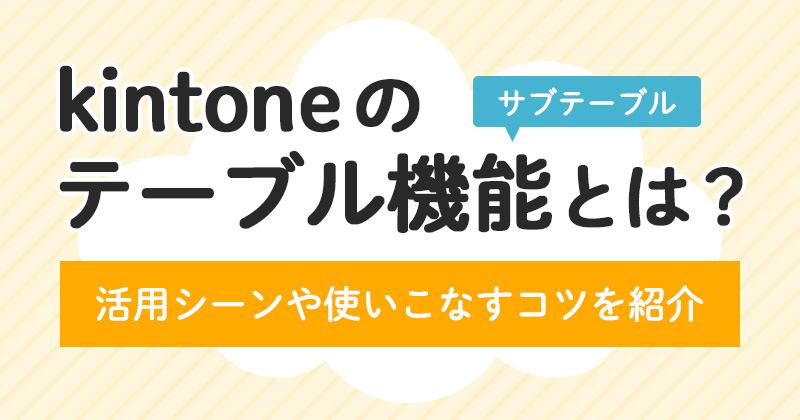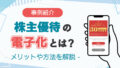kintoneを使っている最中に、「データ入力を効率化したい」「一覧画面をわかりやすくしたい」と感じたことはありませんか。テーブル(サブテーブル)と呼ばれる機能を活用すると、このような課題を解決できる可能性があります。
kintoneのテーブルは、エクセルの表に近い感覚で扱える機能です。関数による自動計算も行えるため、本格的なシステム構築にも活用できます。
本記事では、kintoneのテーブル機能の概要に加えて、実際の活用シーンや使いこなすコツをご紹介します。
kintoneのテーブル機能とは?
kintoneのテーブルは、ひとつのレコード内で複数の行を追加・削除できる機能です。表のようなフィールドを配置できるため、1画面でデータを管理したい場合や、同じ項目を複数回にわたって入力する際に役立ちます。
注文管理アプリを例にして、テーブル機能を使うとなにが変わるのかを見てみましょう。

「製品コード・品名・単価」にテーブル機能を使ったことで、同じフィールドを並べる必要がなくなりました。また、レコードの登録画面では自由に行を増やせるため、同じ顧客からの注文が増えてもスムーズに対応できます。
ただし、不要なフィールドまでテーブル化すると、思わぬ弊害に悩まされることもあります。以下では、テーブル機能の主なメリット・デメリットをまとめました。
| テーブル機能のメリット | テーブル機能のデメリット |
|---|---|
|
|
重要なポイントについては、後述で詳しく解説します。
テーブルとサブテーブルの違い
kintoneのサブテーブルは、テーブル機能の旧称です。現在でもサブテーブルの表記は見られますが、2024年1月版として公表されたサイボウズ社の資料では、すでに「テーブル」の呼称が使われています。
参考:サイボウズ株式会社「kintone テーブルの基本を学ぶ|便利に使おうガイドブック」
サブテーブル化やサブテーブル内といった用語も、「フィールドをテーブル化すること」「テーブル内のデータ」と同じ意味になります。
テーブルと関連レコードの違い
kintoneの関連レコード一覧は、条件が一致するレコードを別のアプリから引用するフィールド機能です。たとえば、注文管理アプリに登録されているA社との取引データを、顧客リストに一覧表示したい場合などに使用します。
参考:サイボウズ株式会社「関連レコード一覧とは | kintone ヘルプ」
テーブル機能と見た目は似ていますが、関連レコード一覧は別アプリのレコードを引用したものです。表示中のアプリではレコードとして扱われないため、登録画面からの直接編集はできません。

引用元に該当のデータがない場合は、空欄になります。
テーブルとの違いをわかりやすくするために、以下では各機能の活用例をまとめました。
- 売れた商品や単価、販売数をまとめて入力し、一覧表の形で管理する
- 電話口で話しながら、取引先からの発注内容をリアルタイムに記録する
- 資料管理アプリにデータを追加する度に、変更履歴(日時)を残す
- 特定の顧客に紐づく売上データをまとめて確認する
- 問い合わせ管理において、直近の対応内容を表示する
- プロジェクト管理用のアプリに、直近のタスクを表示する
簡単にまとめると、テーブル機能はレコードの直接編集が必要なシーンに、関連レコード一覧はデータを確認したい場合に向いています。
kintoneでテーブルを設置する方法
kintoneでテーブルを設置する方法は、以下の2つです。
- 設置済みのフィールドをテーブル化する
- テーブルフィールドを設置し、入力項目を追加する
いずれの方法も「ポータル>指定のアプリ>アプリを設定」から設定画面に移動し、フィールドの編集を行います。まずは、設置済みのフィールドをテーブル化する手順から見てみましょう。
- テーブル化したいフィールドを横一列にする
- 右端に表示される「テーブルの設定」を選択する
- 内容を確認して「この行をテーブルにする」を選択する

「テーブルの設定(オレンジの枠)」ボタンが表示されます。
上記の3ステップで作業は完了ですが、テーブル化した行は元に戻せません。また、テーブル化できない項目(※)が含まれる場合は、事前にフィールドを調整する必要があります。
(※)ラベル、関連レコード一覧、スペース、罫線、グループ、レコード番号、作成者、更新者、作成日時、更新日時が含まれる行は、テーブル化できません。
次に、テーブルフィールドを設置し、あとから入力項目を追加する手順をご紹介します。
- 画面左側の「テーブル」を選択し、設置したい場所にドラッグ&ドロップする
- 同じ流れで、追加したい項目(フィールド)をドラッグ&ドロップする
- 各フィールドの設定画面で、フィールド名や登録ルールを調整する

フィールドの設定画面(オレンジの枠)に移動できます。
取り返しがつかないミスを防ぎたい方には、先にテーブルフィールドを設置する方法がおすすめです。テーブルの設置場所が決まれば、入力画面をイメージしやすくなるため、全体のレイアウトも決めやすくなります。
テーブル機能の活用シーンと使い方のコツ
kintoneのテーブル機能にはさまざまな使い方があるため、事例からイメージをつかむことが重要です。ここでは、わかりやすい活用シーンを例に挙げながら、テーブル機能を使いこなすコツをご紹介します。
SUM関数で経費を自動計算(経理・総務部門)
kintoneで作成したテーブルは、一部のExcel関数に対応しています。SUM関数のほか、四捨五入に使うROUNDUP関数なども使用できるため、細かい計算を自動化するシステムを構築できます。
参考:サイボウズ株式会社「演算子と関数の一覧 | kintone ヘルプ」
以下では、勘定科目ごとに経費を自動計算するシステムを想定して、実際の手順をまとめました。
- 経費入力用のフィールド(勘定科目名)を作成する
- フィールドを横並びにして、テーブル化する
- テーブル直下に、合計金額を表示するフィールド(計算)を設定する
- 各計算フィールドに「SUM(フィールドコード)」を入力する
SUM関数のカッコ内には、計算対象のフィールドコードを入力します(※フィールド名ではありません)。実際にデータを登録してみると、以下のレコードが出力されました。

取引先別やプロジェクト単位などの経費計算も可能です。
IF関数と組み合わせれば、一定額を超えた場合に「要チェック」と表示させるようなシステムも構築できます。
行数カウンタで訪問件数を自動計算(営業部門)
kintoneで登録したレコードは即座に反映され、別のユーザーも内容を確認できます。そのため、現地で営業データ(訪問記録)を次々と登録し、オフィスで集計するようなシステムも構築可能です。
ただし、kintoneの標準機能でテーブルの行数はカウントできません。訪問件数を自動計算するには、行数カウンタと計算フィールドを実装する必要があります。
どのような方法で実装するのか、システム全体の構築手順を見てみましょう。
- 営業データ入力用のフィールドを作成する
- フィールドを横並びにして、テーブル化する
- テーブルに数値フィールド(行数カウンタ)を設置し、初期値を1にする
- テーブル直下に、訪問件数を表示する計算フィールドを設定する
- 計算フィールドに「SUM(カウンタのフィールドコード)」を入力する
上記の手順を踏むと、営業データが増えるたびに行数カウンタが追加され、訪問件数が1ずつ増えていきます。実際にシステムを構築すると、以下のレコードが出力されました。

IF関数とSUM関数を組み合わせれば、特定の文字列を含む行のみ(地域や商品名など)をカウントすることも可能です。
CONTAINS関数でステータスを自動変更(プロジェクト管理)
CONTAINS関数は、指定した文字列と完全一致するデータがある場合に、TRUE(真)を返してくれる関数です。IF関数と組み合わせれば、全タスクの完了後にステータスを変更するような仕組みを構築できます。
以下では新商品のマーケティングを例にして、実際の手順をまとめました。
- タスク入力用と進捗入力用のフィールドを作成する
- フィールドを横並びにして、テーブル化する
- テーブル直下に、ステータス表示用の文字列フィールドを設置する
- 文字列フィールドの設定で「自動計算する」にチェックを入れる
- 計算式に「IF(CONTAINS(フィールドコード, “未対応”), “要チェック”, “完了”)」を入力する
上記の関数は、テーブルにひとつでも「未対応」が含まれている場合に、「要チェック」のステータスを表示する仕組みです。すべてのタスクが「対応済」になると、ステータスを「完了」に変更するシステムになります。

プロジェクトの状況に「要チェック」が表示されています。
テーブル機能はさまざまなシーンに活用できますが、実際のシステム構築では不具合に悩まされることもあります。特に大がかりなシステムを組む場合は、別アプリや外部サービスとの連携も検討しなければなりません。
kintoneの設計・運用でお悩みの方には、トライコーンの「kintone導入支援・設定代行サービス」がおすすめです。当社の導入支援サービスでは、API連携やJavaScriptによるカスタマイズまでサポートしています。
初期段階のシステム設計はもちろん、納品後の伴走支援まで行っておりますので、下記のページからぜひお気軽にお問い合わせください。
テーブル機能の注意点と対処法
テーブル機能はエクセル感覚で使えますが、以下のような失敗も起こりがちです。
- 引用元にフィールド名を入力し、関数が機能しなくなる
- 行数が増えすぎた影響で、意図せずデータを上書きしてしまった
- 不要な行を削除したところ、行数カウンタにズレが生じた
- CSVに書き出したファイルと、既存データの整合性が取れない
運用後の失敗を防ぐには、どのような点を意識すればよいでしょうか。ここからは、テーブル機能の注意点と対処法について解説します。
1.容量が増えると表示に時間がかかる
テーブル機能の行数は手軽に増やせますが、容量に応じて表示速度は下がります。表示までに時間がかかり過ぎる場合は、複数のアプリに分けて運用したり、テーブルを減らしたりなどの工夫が必要です。
また、ユーザーがkintoneに慣れていないと、空行を増やしてしまう可能性も考えられます。運用体制にも目を向けて、事前にテーブル化の目的や使い方をきちんと伝えましょう。
2.システムが複雑になりやすい
テーブルを使うと見た目はすっきりしますが、システム自体は複雑化しやすくなります。特に計算フィールドや条件付き表示フィールドを多用すると、紐づいているデータがわからなくなり、ブラックボックス化が進むかもしれません。
kintoneを使いこなすには、仕様に合わせた設計を心がけることが重要です。あくまでテーブルはひとつの選択肢と認識して、以下のような代替策も検討しましょう。
- 計算フィールドや条件付き表示フィールドは、テーブル外で使用する
- 集計が不要なデータはレコード単位で管理する
- 一覧化が目的の場合は、関連レコード一覧で実装できないかを模索する
上記に加えて、編集時のルール(行の追加・削除・編集)を文書化して共有すると、運用時のトラブルを防ぎやすくなります。
3.標準機能では並び替えができない
kintoneの標準機能では、テーブル内のデータを並び替えることはできません。どうしても並び替えが必要になった場合は、以下の手段を選ぶ必要があります。
- CSVファイルに書き出し、エクセル上で並び替える
- JavaScriptでカスタマイズする
- ソート機能があるプラグインを導入する
基本的には手間がかかるため、まずは並び替えが不要になるシステムを目指すことが重要です。実際の運用をイメージしながら、テーブル内のフィールドやレイアウトを慎重に検討しましょう。
4.ルックアップでの参照ができない
ルックアップとは、別アプリに登録されたレコードを参照し、データを自動入力する機能です。テーブル内にも別アプリのデータは読み込めますが、テーブルをルックアップの参照元にすることはできません(※後述のプラグインを導入すれば可能)。
そのため、参照するデータは別のフィールドで管理したり、土台になるシステムではテーブルの使用を控えたりなどの工夫が必要です。
テーブル機能を使いこなすプラグイン3選
kintoneのテーブルでは一部機能が制限されますが、プラグインを導入すると問題が解決することもあります。以下では、テーブル機能をさらに使いこなすプラグインをご紹介します。
1.ルックアップ内サブテーブルコピープラグイン
合同会社ぱんだ商会が提供する、テーブルを別アプリのテーブルにコピーできるプラグインです。ルックアップの仕組みとは異なりますが、複数行でもそのままの形でコピーされるため、データの参照や移動に役立ちます。
参考:合同会社ぱんだ商会「LookupTable | TIS」
本プラグインでテーブルをコピーするには、参照先のアプリで行番号フィールドが必要になります。余計な表示項目を増やしたくない方は、特定のフィールドを非表示にできるプラグインを活用しましょう。
2.テーブルデータ転送+
JBCC社が提供するテーブルデータ転送+も、テーブル内のデータを別アプリにコピーできるプラグインです。ルックアップ内サブテーブルコピープラグインとの違いは、1行分のデータが1レコードとして登録される点にあります。
コピー先では通常のレコードと同じ形式になるため、テーブル内のデータをグラフ化したい場面に向いています。
参考:JBCC株式会社「ATTAZoo+ 『テーブルデータ転送+』設定&活用方法 | 『ATTAZoo+』 設定&活用イメージ | ブログ | 」
3.テーブル一覧表示プラグイン
アディエム社が提供する、レコード一覧画面を編集するためのプラグインです。導入すると、クリックをしなくてもテーブル内が表示されるようになり、各項目の表示・非表示も自由に切り替えられます。
そのほか、通常フィールドの項目を結合したり、複数のカスタマイズビューを設定できたりなど、テーブル以外の編集機能も充実しています。
参考:株式会社アディエム「テーブル一覧表示プラグイン for kintone」
【番外編】gusuku Customine
アールスリーインスティテュート社のgusuku Customineは、kintoneの標準機能を拡充できるプラットフォームです。ボタンひとつでプログラムを生成するなど、ノーコードでのカスタマイズもサポートしてくれるため、高度な知識がなくても本格的なシステムを構築できます。
プラグインではありませんが、テーブル内の情報を別アプリに転記する機能も備わっています。PDFの帳票出力にも対応しているため、kintone内のデータを文書化(見積書や請求書など)したい企業にもおすすめです。
参考:アールスリーインスティテュート「あなたのkintoneにノーコードの魔法を- gusuku Customine(グスク カスタマイン)」
kintoneの仕様を踏まえてテーブルを使いこなそう
kintoneのテーブルは、データの入力や確認作業を効率化できる機能です。関数などの関連機能を使いこなせば、高度なシステムも実装できるようになります。
ただし、多用によって失敗を招くこともあるため、注意点も理解したうえでシステム設計をすることが重要です。実際の運用をイメージしながら、kintoneの仕様に合ったシステムを構築しましょう。