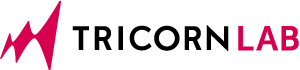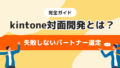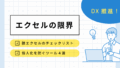ノーコード・ローコードツールのkintoneは、3万社以上が導入する業務改善ツールです(※2023年6月時点)。小売業や製造業をはじめ、さまざまな業界課題を解決していますが、導入時には向き・不向きを踏まえてシステム設計をする必要があります。
本記事では、他のツールとの違いにも触れながら、kintoneの強みと弱みをわかりやすく整理しました。導入効果を高めたい企業に向けて、開発体制を整えるポイントもまとめています。
kintoneの強み・弱みは? 他ツールとの比較表
kintoneの得意分野は、IT部門に依存しない現場主導型の課題解決です。大規模システムの一部としては運用できますが、基本的には小さな課題が生じやすいバックオフィス業務など、中小規模のシステム構築に向いています。
kintoneの特性をわかりやすくするために、主なビジネスツールとの比較表を以下にまとめました。
| 比較項目 | kintone | Excel(ローカル) | オンライン スプレッドシート | Webデータベース |
| 同時編集 | ○ | × | ○ | サービスによる |
| リアルタイム共有 | ○ | × | ○ | ○ |
| データ容量 | ユーザー数×5GB | パソコンに依存 | 15GBまで (※無料の場合) | 〇~◎ (構成による) |
| カスタマイズ性 | 高い | 低い | 低い | 中~高 |
| プラグイン | ◎ (種類が豊富) | △ (拡張機能あり) | △ (拡張機能あり) | △~〇 (サービスによる) |
| API連携 | ◎ (種類が豊富) | × | 〇 | 〇 |
| Javascript | 〇 | × | △ | △~〇 (サービスによる) |
| 権限管理 | 〇 | × | △ | 〇 |
| モバイル対応 | 〇 | △ | △ | △~〇 (サービスによる) |
| 大規模システム | 不向き (一部としては可) | 不向き | 不向き (一部としては可) | △~〇 (サービスによる) |
| 月額料金 | 1ユーザーあたり 月額1,000円~ | 無料 (導入コストあり) | 基本的に無料 | 1ユーザーあたり 月額1,500円~ |
※実際の機能やカスタマイズ性、料金はサービスによって異なるため、詳細は各サービスの製品情報をご確認ください。
上記の内容を踏まえて、ここからはkintoneに向いている業務・不向きな業務を解説します。
kintoneに向いている業務
kintoneに向いているのは、現場で改善のアイデアが出やすい業務や、バックオフィスなどの属人化しやすい業務です。また、経営分析に役立つグラフ機能やプラグインがあるため、日々のデータを蓄積したい業務にも向いています。
- 日報や作業報告書の作成
- 各社員のタスクや営業案件などの管理
- 顧客情報の登録や管理
- 契約書や申請書の管理
- 承認フロー(ステータス管理)の電子化
外部サービス(API連携)を活用すると、より高度な業務にも対応可能です。たとえば、Webフォームの入力内容を自動登録したり、特定の顧客にメールを一括送信するようなシステムが構築できます。
kintoneに不向きな業務
kintoneにはAPIリクエスト数などの制限があるため、ビッグデータを扱うような高付加処理や、大規模なシステムの構築には不向きです。そのほか、社外のユーザーとの密なやり取りや、業界特有の要件対応にも向いていない可能性があります。
- 数十万件を超えるようなデータの管理・分析
- 工場機器との連携など、データの更新回数が多い制御処理
- ERPのような、大規模な全社横断型システムの構築
- 外部顧客向けの大規模なポータルサイト運営
- ECサイトや決済システムのバックエンド業務
ただし、大規模なシステムの一部としては運用できるため、エンタープライズ企業にもkintoneを活用する余地はあります。
kintoneの強みは? 成功事例から見る得意分野

kintoneの強みは、現場主導で手軽に業務改善を進められることです。データの一元化にも役立つうえに、プラグインや外部サービスを活用すると、より高度な業務にも対応できます。
これらの強みを踏まえると、kintoneは次のような企業に向いています。
- 紙やExcelでデータ管理をしており、業務の効率化や見える化を図りたい
- Excelの複雑なマクロなど、作業の属人化に悩んでいる
- 各店舗の受注状況や案件状況を、リアルタイムで把握したい
- 散らばったデータを集約し、経営分析に活用したい
- バックオフィス業務を自動化したい
ここからは成功事例も含めて、kintoneの強みや得意分野をひとつずつ解説します。
1.現場主導でアイデアをすぐ形にできる
kintoneのアプリ制作は、高度なプログラミング知識が不要です。100以上のサンプルアプリや既存のExcelファイルをそのまま活用して、さまざまな業務アプリを手軽に作成できます。
- 1.サンプルアプリをベースにする
- 2.Excelファイルを読み込む(売上データ、顧客リストなど)
- 3.CSVファイルを読み込む(在庫管理データ、部材管理データなど)
- 4.別のアプリを再利用する(テンプレートも作成可能)
- 5.はじめから作成する
kintoneのプラットフォームには、チーム・部署単位で情報を集約するための「スペース」も用意されています。スペースごとにアプリをまとめて管理できるため、事前に運用ルールを定めておけば、アプリが散在して混乱を招くといった事態も防げます。
これらの機能により、「売上を自動計算したい」などのアイデアをすぐ形にできるため、kintoneは現場主導で業務改善を進めたい企業に向いています。
ファイルサーバーの混乱を解消するため、5ユーザーでkintoneを導入した事例です。サンプルアプリをほぼそのまま活用し、営業活動データを集約するシステムを構築しました。
参考:サイボウズ株式会社「ミエデン – kintone(キントーン)導入実績30,000社 – 導入事例 | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
2.非IT部門でもアプリをカスタマイズできる
kintoneで制作したアプリは、入力項目や表示項目を自由に調整できます。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で扱えるため、非IT部門でも目的に合わせたカスタマイズが可能です。

各アプリの管理画面から、入力項目や表示項目をカスタマイズできます。
登録データを増やしたい場合も、新たにアプリを作り直す必要はありません。たとえば、既存の顧客管理アプリに「来訪回数」の項目を追加すると、すぐに入力画面・表示画面へ反映されます。
kintoneは柔軟性が高いため、業務環境の変化にも素早く対応できるでしょう。
あくまでノーコードツールとしての活用にこだわり、JavaScriptなどを使用せずに製造現場を改革した事例です。各社員の案件情報を共有するシステムを構築し、製造データから販売データまでの一元管理を実現しました。
参考:サイボウズ株式会社「芙陽工業 – kintone(キントーン)導入実績30,000社 – 導入事例 | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
3.プラグインや連携サービスが豊富
kintoneとプラグイン・外部サービスを組み合わせると、効率化・自動化できる業務の幅がさらに広がります。2025年7月現在では、200以上のプラグインや連携サービスが用意されているため、高度な業務プラットフォームとしても運用できます。
参考:サイボウズ株式会社「サービスを探す – kintone(キントーン)- プラグイン・連携サービス | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
- 帳票プラグインを導入して、kintoneの売上データを帳票出力する
- プラグインでカレンダー機能を追加し、直感的にスケジュールを把握しやすくする
- 外部のWebフォームと連携し、入力内容をkintoneに自動登録する
上記のような機能拡張についても、基本的にはノーコード・ローコードで対応可能です。パッケージ化されたプラグインや連携サービスが多いため、システムの開発期間やコストを大幅にカットできるでしょう。
kintoneと会計ツールの「freee」を連携し、案件管理から月次処理までを一元化した事例です。経理部が確認した発注内容を、ワンクリックで自動仕訳するシステムが構築されています。
参考:サイボウズ株式会社「ランドスケイプ – kintone(キントーン)導入実績30,000社 – 導入事例 | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
kintoneとWebフォームの連携については、CRMプラットフォームの「クライゼル(kreisel)」を活用する方法がおすすめです。クライゼルには高度なフォーム機能のほか、顧客データベースの構築やメール配信をする機能も備わっています。
kintoneと連携すると、取引先などがフォームに入力した内容を自動登録し、顧客リストとしてデータを蓄積できます。2025年3月には、相互のAPI連携をサポートする「kreisel Webhook クリエイター for kintone」「kreisel コネクター」もリリースされたので、クライゼルの活用をぜひご検討ください。
4.リアルタイムの情報共有や更新が可能
kintoneはリアルタイム性が高く、アプリ上のデータ入力や更新がすぐに反映されます。スマートフォンやタブレットにも対応しているため、たとえば営業先で入力した実績データを、すぐに社内のマネージャーや担当者へ共有できます。
また、ルックアップと呼ばれる機能を使うと、別のアプリに登録されたデータを参照(自動登録)することも可能です。

上図では「受注・売上管理」に登録したデータが、「顧客リスト」に自動追加される。
ルックアップ機能でアプリ同士を紐づければ、同じデータを入力する必要がなくなるため、入力ミスや重複入力、入力形式の不一致などを防げるでしょう。
ルックアップ機能を活用し、商品マスタアプリと販売管理アプリを連携した事例です。商品名や単価の自動取得により、見積作業や請求業務を効率化することに成功しました。
参考:サイボウズ株式会社「キントーン活用事例 株式会社京屋染物店 様」
5.蓄積したデータで経営分析ができる
kintoneの各アプリには、データをグラフ化できる機能が備わっています。たとえば、kintoneに売上データを登録した場合は、週次や月次の売上推移を見える化したり、取引先別の売上をグラフ化させることが可能です。

折れ線グラフや棒グラフのほか、円グラフや面グラフ、クロス集計表も選択できる。
見た目はシンプルですが、データの抽出条件を設定する機能や、複数の方法でデータ集計する機能などが備わっています。前述のプラグインや外部サービス、ルックアップ機能などとの併用により、高度な経営分析もできます。
顧問先別での対応件数や、各担当者のタスク量をグラフ化した事例です。「作業中」のタスク量が一目瞭然になったことで、業務が集中している社員を特定しやすくなり、タスクの最適な振り分けを実現しました。
参考:サイボウズ株式会社「キントーン活用事例 辻野社会保険労務士事務所 様」
6.安心できるセキュリティ体制
kintoneは外部機関からのセキュリティ評価が高く、「ISMAP」や「ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ)」の認証を受けています。また、ツール自体にも下記の機能が備わっているため、管理者側で強固なセキュリティを築くことも可能です。
- IPアドレス制限の設定
- クライアント証明書による接続端末の認証(セキュアアクセス)
- 認証アプリによる2段階認証
- 1ユーザー単位でのアクセス権設定
各ユーザーのアクセス権については、アプリ単位で設定することもできます。適切にアクセス権を管理すれば、機密情報の漏えいを防ぎつつ、一般社員が手軽にアプリを制作できるような環境が構築されます。
高いセキュリティ水準が求められる、金融機関の活用事例です。事業部全体で1,700名ほどがユーザー登録し、200を超えるアプリで店舗間の情報共有が加速しました。
参考:サイボウズ株式会社「みずほ信託銀行 – kintone(キントーン)導入実績30,000社 – 導入事例 | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
kintoneの弱みは? 主な苦手分野と対策

kintoneの弱みは、スケールの大きいシステムに不向きな点です。また、基本的には社内での活用が想定されていることから、以下の企業には向いていない可能性があります。
- 日常的に数十万件以上のデータを取り扱っている
- 全国に拠点があり、数百人規模の同時アクセスが多発しやすい
- 取引先や顧客と、リアルタイムでコミュニケーションを図りたい
- ガイドラインに則った厳格かつ専門的な業務フローが求められる
ここからは、kintoneの弱みや苦手分野をひとつずつ解説します。
1.ビッグデータの蓄積や分析
kintoneのレコード数(1行あたりのデータ)に上限はありませんが、大量のデータを登録すると動作に影響する可能性があります。また、アップロードできるExcelファイルの容量や、作成できるグラフ数には制限があるため、基本的にビッグデータの蓄積や分析には向きません。
| ビッグデータの管理に関わる項目 | 上限 |
| アップロードできるExcelファイル | 1MB、1,000行、500列まで |
| CSV・TSV・TXTファイル | 100MB、10万行まで |
| 作成できるグラフ | 1アプリにつき1,000件まで |
| フィールド | 1アプリにつき500個まで |
| テーブル | 10フィールド、100行まで(※推奨値) |
| JavaScriptファイル・CSSファイル | 20MB、1アプリにつき30個まで |
数十万件を超えるようなビッグデータを管理する場合は、10年単位で複数のアプリに分けるなどの工夫が必要です。管理面はやや複雑になりますが、ルックアップ機能やプラグインを活用すれば、効率的にデータを集計できる場合もあります。
たとえば、トヨクモ社が提供する「DataCollect(データコレクト)」は、複数アプリ間のデータを簡単に集約できるプラグインです。ただし、集約できるレコード数には上限があるため(※)、数十万件を超えるようなデータの取り扱いには注意してください。
(※)通常プランで1万件まで、有料オプションで最大10万件まで。
参考:サイボウズ株式会社「DataCollect(データコレクト) – kintone(キントーン)- プラグイン・連携サービス | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
2.大規模な基幹系システムの構築や統合
kintoneでは、大規模利用に特化したワイドコースも用意されていますが、外部サービスとのデータのやり取り(APIリクエスト数)には上限があります。1アプリあたりの上限数は「10万回/日」であるため、大規模な基幹システムの構築は難しいかもしれません。
- レコードの取得・追加・更新
- アプリ構成(フィールドコードやフィールド名など)の取得
- 添付ファイルのアップロード など
たとえば、外部の倉庫管理システムと連携し、入出庫のたびにkintoneへデータ送信をするシステムがあるとします。
この場合、1時間あたり5,000回の入出庫が生じると、24時間では12万回のデータ更新が必要です。つまり、kintoneのAPIリクエスト上限数を超えるため、ひとつのアプリでは運用できない計算になります。
主な対策としては、時間帯をずらしてリクエストを送信したり、複数のレコードを一括登録したりする方法があります。ただし、その分システムが複雑になるため、設計や実装が難しくなるかもしれません。
kintoneの導入に不安がある方には、「kintone導入支援・設定代行サービス」がおすすめです。当社の支援サービスでは、お客様へのヒアリングを通して課題を特定し、最適なソリューションをご提案させていただきます。
納品後のアフターフォローも行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、kintoneはエンタープライズ企業のDXを支援しており、専用のワイドコースではさまざまな機能を拡充できます。下記の特設サイトでは、大規模利用時に役立つプラグインや導入事例、セミナー情報なども公開されているので、ぜひ参考にしてください。
kintone(キントーン)エンタープライズ企業の方向け特設サイト
3.社外のユーザーや顧客とのやり取り
kintoneは、主に社内での業務改善や情報共有を目的にしているため、社外のユーザーや顧客とのやり取りには不向きです。外部ユーザーを招待する「ゲストスペース」もありますが、ゲストユーザーには以下の制限がかかります。
- ほかのスペースやポータルにはアクセスできない
- スマートフォン用の「kintone モバイル」が利用できない
- 組織単位での宛先指定ができない(※ゲストスペース共通)
また、ゲストユーザーにも月額料金(1ユーザー700円~)がかかるため、ゲストスペースで問い合わせ環境を作るような構想は難しいでしょう。
問い合わせ対応を効率化するには、前述のクライゼルでWebフォームを作成し、kintoneと連携する方法があります。kintoneのデータを活用し、特定の顧客のみにメールやサイトを配信することもできるため、クライゼルはウェブマーケティング全般の改善に役立ちます。
4.業界特有の高度な要件への対応
業界特有の高度な要件とは、たとえば製造業におけるトレーサビリティ対応や、医療分野のガイドライン対応などがあります。これらの業務をデジタル化するには、複雑な条件分岐やフロー構築が必要になるため、kintone単体での対応は難しいかもしれません。
また、kintoneの同時アクセス数は、1ドメインにつき100ユーザーまでです。したがって、全国を走り回っている配送業者がリアルタイムで進捗報告をするようなシステムでは、レスポンスの低下を招くリスクがあります。
業界特有の要件にも対処したい場合は、kintoneと外部サービスの併用を検討しましょう。たとえば、特化型の基幹システムで主要業務を運用し、バックオフィスの補助役としてkintoneを活用するような方法が考えられます。
kintoneの導入効果を高めるポイント
kintoneは現場主導でアプリを開発・調整しながら、徐々に全体最適を目指す企業に向いています。そのため、下記のポイントを意識すると導入効果が高まります。
- 1.業務フローをまとめてからシステム設計をする
- 2.現場主導の開発体制を整える
- 3.アジャイル開発を意識する
- 4.伴走支援がある導入支援サービスを選ぶ
具体的にどのような開発体制が望ましいのか、以下でひとつずつ解説をします。
1.業務フローをまとめてからシステム設計をする
kintoneは柔軟性が高いため、システムの設計次第で使い勝手や将来の拡張性に差が出ます。そのため、まずは現在の業務フローを可視化し、「どこに課題があるか」「どのような課題か」を明確にしましょう。
実際のアプローチとしては、日報の分析や現場へのヒアリングが有効です。また、各業務で発生するタスクを細分化し、矢印や図形で全体の流れを表した業務フロー図を作成すると、潜在的な課題も見つけやすくなります。
業務フロー図の作り方については、下記の記事をご参照ください。
kintoneで業務改善はどこまでできる? 業種別の活用事例14選 | トライコーンラボ
また、システムの修正を減らすには、kintoneでできることを事前に把握しておくことも重要です。サンプルアプリやプラグイン、連携サービスにも目を通したうえで、業務効率化につながるシステムを考えてみましょう。
2.現場主導の開発体制を整える
情報システム部門や外部のベンダーに頼り過ぎると、前述の「現場主導でアイデアをすぐ形にできる」というメリットが薄れます。kintoneは非IT部門でも扱いやすいツールなので、現場を主体とした開発環境を整えましょう。
具体的には、以下のようなアプローチが考えられます。
- だれでも気軽に試作アプリを作れるスペースを用意する
- 各業務のキーマンを非IT部門から選ぶ
- 情報システム部門やIT部門はアドバイザー(支援役)として関与する
- 社内研修を行い、kintoneの有用性を現場に伝える
現場が自走できる環境を整えると、目の前の課題からさまざまなアイデアが生まれ、業務改善のスピードが上がります。
3.アジャイル開発を意識する
非IT部門にkintoneを定着させるには、まず「アプリを作ってみる」「実際に使ってみる」という姿勢が重要です。そのため、最初から完璧なアプリを作るのではなく、修正や改善を前提にしたアジャイル開発を意識しましょう。
アジャイル開発とは、機能単位で「企画・設計・実装・テスト」のサイクルを繰り返す手法です。小さな修正・改善を繰り返すことにより、アジャイル開発では次のメリットが生じます。
- アプリ開発の進捗を実感しやすいため、モチベーションを保ちやすい
- 業務(要件)に変化が生じても、柔軟に対応できる
- 企画や設計のハードルが低いため、現場主導の開発体制を整えやすい
アジャイル開発では、テスト段階で有用なフィードバックを得ることがポイントになります。そのため、アプリの制作者と導入現場の対話を増やし、気づいた課題をすぐに改善できる体制を整えましょう。
4.伴走支援がある導入支援サービスを選ぶ
kintoneの導入時には、システムを運用してから新たな課題が見つかることもあります。課題によっては、Javascriptによるカスタマイズやプラグインの導入が必要になるため、伴走支援型の導入支援サービスを選ぶと安心です。
また、サポートが手厚いサービスは、上層部や情報システム部門を説得する際にも役立ちます。具体的なメリットを早期に把握でき、かつ運用後のトラブルにも備えられるため、導入に向けた社内の不安を解消しやすくなります。
当社の「kintone導入支援・設定代行サービス」では、要件定義やシステム設計の対面サポートも行っております。社内でもkintoneを広く活用しているため、現場や組織に浸透させるノウハウまでお伝えできます。
運用後も含めてトータルでサポートしておりますので、kintoneの導入・運用に不安を抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
kintoneの強みを活かす方法を考えよう
kintoneに限らず、どのようなツールにも向き不向きがあります。ただし、kintoneでは豊富なプラグインや連携サービスが用意されているため、アイデア次第では苦手分野を克服できるかもしれません。
また、小規模~中規模のデータはkintoneで管理し、外部の基幹システムと連携するような使い方もあります。さまざまな事例を参考にしながら、kintoneの強みを最大限活かせる方法を考えてみましょう。