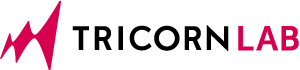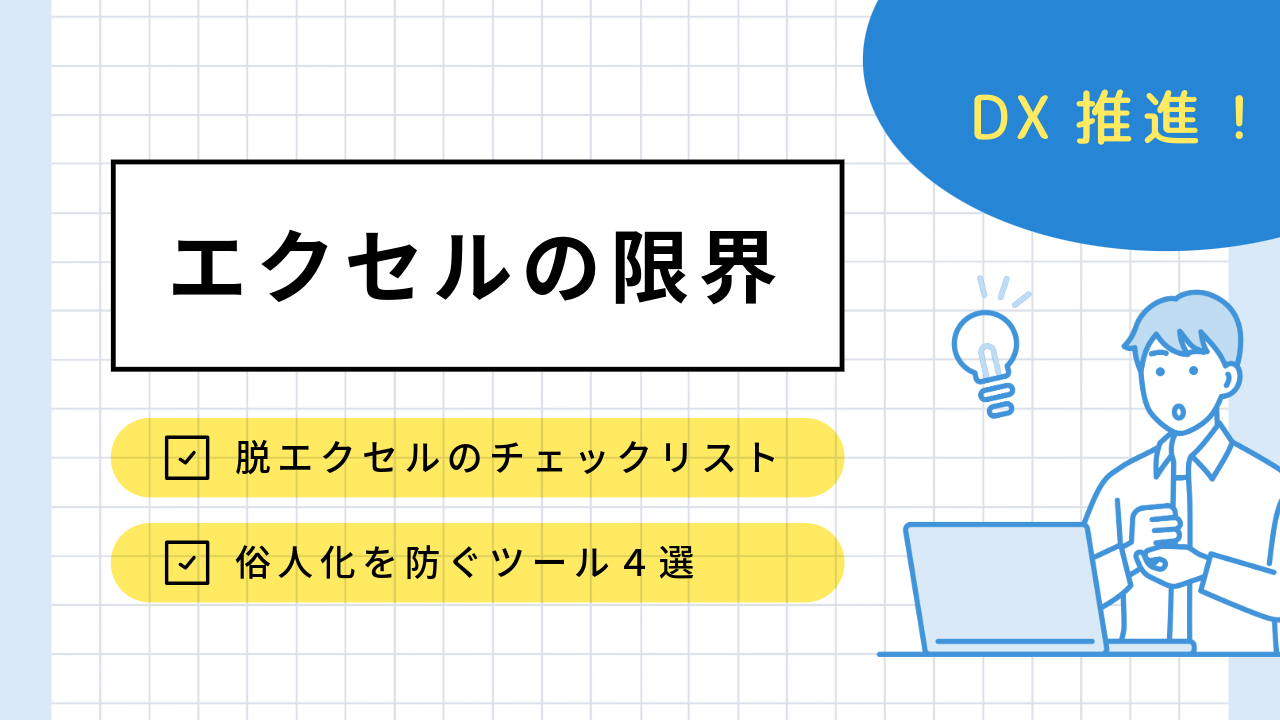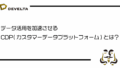表示速度の遅さや度重なるデータ消失など、Excelの運用に限界を感じていませんか?
Excelはさまざまな業務に活用されていますが、データの一元管理やリアルタイム共有には不向きな側面もあります。なかには、複雑なマクロによって属人化が進み、業務自体がブラックボックス化してしまった事例も。
本記事では「Excelでの運用を見直したい」と感じている方に向けて、脱エクセルのチェックリストや、主な代替ツールの特徴をまとめました。Excelの機能的な限界にも触れながら、課題解決に向けたアプローチを解説します。
Excelの限界はどこ? 脱エクセルのチェックリスト
脱エクセルを実現できるツールには、オンラインスプレッドシートやノーコード・ローコードツールなどがあります。ただし、Excelに適した業務もあるため、システムの移行には慎重な判断が必要です。
わかりやすい判断基準として、以下では脱エクセルのチェックリストを代替ツール別にまとめました。
- ファイルの上書きにより、データを消失したことがある
- 複数人で同時編集ができないことに不便を感じる
- 最新版のファイルが分からなくなり、古いファイルを更新していた
- ファイルの送信に手間がかかっている
- 本来は編集すべきではない社員が、データを書き換えてしまった
- 部署ごとにファイルが分散し、データの一元管理ができていない
- 顧客情報の手入力に時間がかかっている
- データの入力規則にばらつきがある
- 申請や承認のフローを構築できておらず、どこで止まっているか把握できない
- 複雑なマクロをファイルを開くたびに実行している
- データが膨大になり、ファイルを開くだけで1分以上かかる
- 数式が複雑で、参照切れやエラーが発生しやすい
- データの更新漏れや重複入力が頻発している
- データを時系列で管理できていない
- 特定条件でのデータ抽出や分析に時間がかかっている
- 業界特有の会計ルールに対応できていない
- 現場(モバイル端末)からExcelのチェックリストを確認できない
- 契約情報やフォーマットのファイルが分散し、毎回探すことが大変
- リアルタイムの在庫管理ができず、人員配置の最適化もできていない
- 法改正や制度変更がある度に、手作業でExcelを修正している
Excelに限界を感じており、かつ該当する項目が多い場合は、代替ツールでの脱エクセルを考えましょう。
Excelの限界や属人化を放置するリスク
Excelの限界を放置すると、次のようなリスクが高まります。
- 業務品質が低下する(ヒューマンエラーの増加、マクロのブラックボックス化 など)
- セキュリティリスクが上がる(ファイルの誤送信が増える、監査が難しくなる など)
- 業務継続性が低下する(データの復旧ができない、突発的な業務に対応できない など)
- 組織の成長が阻害される(全社的な分析ができない、意思決定が遅れる など)
上記のほか、属人化が進むこともExcelを使い続ける弊害です。たとえば、帳簿ファイルで難解なマクロが組まれていると、一部の人しか関数やデータを調整できないため、業務の引き継ぎが難しくなります。

最悪のケースではファイルが破損する可能性もあるため、できればExcelの限界を感じる前に対策を立てましょう。
Excelの機能的な限界は? 脱エクセルの判断基準
Excelのワークシートには、行列数などの機能的な限界があります。実務に影響しない部分もありますが、基本的に大規模なデータ管理やシステム構築には向いていません。
以下の表は、実務に影響しやすいExcelの限界をまとめたものです。
| 項目 | 機能的な限界 |
| 行数と列数 | 1,048,576行、16,384列(XFD列まで) |
| セル内の文字数 | 入力は32,767文字、表示は1,024文字まで |
| ウィンドウ枠 | ひとつのウィンドウに対して4つまで |
| 計算時の有効桁数 | 15桁 |
| 同時接続ユーザー数 | 256ユーザーまで |
※参考:Microsoft サポート「Excel の仕様と制限」
また、Excelはデータの一元管理やリアルタイム共有には特化していません。オフライン型の表計算ソフトであるため、実務では以下のような限界に直面することもあります。
- データの一元管理が難しい(異なる部署間のデータ統合など)
- 複数人でのリアルタイム共有ができない
- ワークフロー処理が難しい(承認フローやステータス管理など)
- 細かいアクセス制御やログの管理ができない
- スマートフォンからの入力に手間がかかる
ここまでの内容を踏まえて、以下ではExcelに適した業務と適していない業務を解説します。
Excelに適した業務
Excelに適した業務は、個人や少人数のチームが単独で完結できるようなタスクです。データ量がそれほど膨大ではなく、処理内容がシンプルな業務であれば、適切な管理によって作業を効率化できます。
実際にどのような業務が該当するのか、以下では具体例をまとめました。
- 原価や経費の計算
- 商品別や月別などの売上集計
- フォーマットを活用した帳票の作成
- 勤務時間や出欠回数の集計
- リアルタイム性を求められない在庫管理(週ごと、月ごとなど)
- イベントスケジュールの管理(日程や担当者などの一覧作成)
- 顧客リストやアンケート結果の管理(数千~1万件レベルのもの)
上記のように、1シートあたりのデータ量が中規模以下で、作業手順や集計ルールが定型化されている業務は、Excelでも十分に対応できます。
Excelに適していない業務
Excelに適していない業務としては、複雑なワークフロー処理やデータの一元管理が挙げられます。また、Excelはリアルタイム性(反映や共有)には特化していないため、多人数・多拠点で同時にこなすようなタスクも苦手分野です。
実際にどのような業務が該当するのか、一例をご紹介します。
- 数十万件を超えるような、大規模なデータの管理
- 稟議や申請、承認などが必要になる業務フロー(経費や有給の申請など)
- 複数の部署や拠点にまたがるデータ共有(各部門の予算管理など)
- 会計ソフトなど、外部サービスとのデータ連携
- プロジェクト管理など、日次での更新が必要になる共同作業
- 給与計算や社員情報の管理など、アクセス権の管理が必要になる業務
- 各自のスマートフォンでデータ入力をする現場作業
規模によってはExcelでも対応できますが、無理に使い続けるとデータの破損リスクなどが高まります。
Excelに限界を感じたときの代替ツール4選

脱エクセルに活用できるツールとしては、以下の4つが挙げられます。
- オンラインスプレッドシート(Googleスプレッドシートなど)
- ノーコード・ローコードツール(kintoneなど)
- Webデータベース(PigeonCloudなど)
- 業界特化型の支援ツール(製造業向けのERPなど)
いずれのツールも、クラウド型のサービスでは編集内容がリアルタイムで反映されます。ここからは4つの種類に分けて、代替ツールのメリットやデメリット、脱エクセルに向いている業務をご紹介します。
1.オンラインスプレッドシート
オンラインスプレッドシートは、Web上でデータの入力や編集ができる表計算ツールです。代表的なサービスには「Googleスプレッドシート」や「Microsoft Excel for the Web」があり、いずれも複数人での同時編集に対応しています。
基本的な仕様はExcelに近いため、データの処理方法や管理方法を変える必要はありません。サービスによっては、Excelで作成したファイルをアップロードすると、そのまま同じ形式のスプレッドシートが自動作成されます。

関数の「IMPORTRANGE」を使うと、別シートのデータを呼び出すことが可能。
| 脱エクセル時のメリット | 脱エクセル時のデメリット |
| ・複数人での同時編集が可能 ・変更履歴が自動で保存される ・シートやファイル単位で権限管理ができる ・無料で利用できるツールがある ・エクセルライクなツールで、xlsxファイルをそのまま活用できる | ・オフライン環境では変更が反映されない ・容量によっては表示速度や処理速度が遅れる ・データの自動処理には専門知識が必要 ・ワークフロー処理の実装に手間がかかる ・機密情報を扱う場合は、細かいセキュリティ設定が必要 |
- 各店舗の日報や週報の集計
- ガントチャートを使ったスケジュールや進捗の管理
- 小規模な予算管理(1~3部門、ユーザー数10人程度まで)
- 給与計算を含む勤怠管理
- Excelを導入していないパートナーやクライアントとの共同作業 など
なお、オンラインスプレッドシートの処理速度はExcelより低い傾向にあります。あくまで表計算ツールの一種なので、システム的な運用やビッグデータ(数万以上)の構築には向いていません。
2.ノーコード・ローコードツール
ノーコード・ローコードツールとは、直感的な操作でアプリケーションやソフトウェアを開発できるツールです。プログラミングなどの専門知識が不要なため、非IT部門でも目的に合ったシステムやワークフローを構築できます。
たとえば、サイボウズ社の「kintone(キントーン)」は、100種類以上のサンプルアプリやxlsxファイルから業務アプリを作れるツール。別のアプリを参照するルックアップ機能や、プラグインまたは外部サービスとの連携機能も備わっているため、あらゆるデータの一元管理を実現できます。
参考:サイボウズ株式会社「kintone(キントーン)- あなたの「その仕事に」」
また、インプリム社の「Plesanter(プリザンター)」は、完全無料で全機能を使えるオープンソースのツールです(※一部アップグレードは有料)。オンプレミス型も提供されているため、オフライン環境でも用途に合ったシステムを構築できます。
参考:株式会社インプリム「プリザンター|OSSのノーコード・ローコード開発ツール」

プラグインや外部サービス連携で、一元化できるデータや自動処理の幅が広がる。
| 脱エクセル時のメリット | 脱エクセル時のデメリット |
| ・データの一元管理を実現しやすい ・複雑なワークフローも自動化できる ・プログラミングやマクロの知識が不要 ・各ユーザーの権限を細かく設定できる ・現場のアイデアをすぐ形にできる | ・基本的に月額料金がかかる ・基幹システムとしての運用には限界がある ・サービスによってはAPI連携が限定的 ・業界特有のワークフローには対応していない(※アイデア次第で実装は可能) |
- 全社的な売上管理や勤怠管理
- 申請・承認・管理フローが必要になる経費管理や予算管理
- 小~中規模の在庫管理
- 顧客情報などの一元管理をするCRM(顧客関係管理)
- 案件管理や営業目標管理を含めた営業支援(SFAツールの構築) など
大規模または業界特化型のシステムを組むことは難しいですが、ノーコード・ローコードツールは仕組みが分かりやすいため、Excelで起こりがちな属人化を防げます。CRMツールやSFAツールの構築に興味がある方は、下記の記事もご参照ください。
kintone(キントーン)をCRM(顧客管理)に活用!業務効率もアップ | トライコーンラボ
kintone(キントーン)をSFAとして活用!機能や活用事例、おすすめのプラグインも紹介 | トライコーンラボ
3.Webデータベース
Webデータベースは、データの登録や蓄積、参照などに特化したクラウド型のツールです。代表的なサービスには「PigeonCloud(ピジョンクラウド)」や「楽々Webデータベース」などがあり、設計次第では数十万件~数百万件のビッグデータを管理できます。
データ容量に強みがある一方で、画面のカスタマイズ性はそれほど高くありません。柔軟性が求められる場合はノーコード・ローコードツール、膨大なデータを取り扱う場合はWebデータベースを選ぶなど、業務の特性や目的に合わせて使い分けましょう。

サービスによっては、外部サービスとの連携も可能。
| 脱エクセル時のメリット | 脱エクセル時のデメリット |
| ・大容量のデータを蓄積できる ・データの構造化により一元管理が容易になる ・データの検索や抽出が容易 ・データの紐づけに関数などが不要 ・各ユーザーの権限を細かく設定できる | ・基本的に月額料金がかかる ・複雑なワークフローの構築は難しい ・初期設定が甘いと、修正に手間がかかりやすい ・サービスによってはカスタマイズ性が低い ・オンライン環境が必須になる |
- 数百以上の支社や支店、部署などのデータ管理
- 日報や週報の長期的な保存(データの作成と蓄積)
- 契約書や見積書などのドキュメント管理
- 営業報告や商談履歴の記録
- ビッグデータからの抽出や分析 など
なお、Webデータベースはサービスによって特徴が異なります。上記に該当しない場合もあるので、実際のサービスを確認しながら検討しましょう。
4.業界特化型の支援ツール
専門性が高いワークフローや大規模な基幹システムを構築するには、業界特化型のツールが必要です。たとえば、製造業向けのERP(基幹システム)には、受発注に伴って在庫調整をする機能や、納期に合わせて生産計画を策定するなどの機能が備わっています。
サービスによって仕様が大きく異なるため、メリットやデメリットを一概にまとめることは難しいですが、全体としては以下の特徴があります。
| 脱エクセル時のメリット | 脱エクセル時のデメリット |
| ・各業界に特化した機能が備わっている ・計画策定からデータ収集までを一元化できる ・作業現場からでもデータを入力しやすい ・サポート体制が充実している傾向にある ・法改正や制度変更への対応が早い | ・導入コストが高い ・自社に合ったツールを探す必要がある ・通常の業務や部門には導入しづらい場合もある ・独自仕様が多いツールを選ぶと、別ツールへの切り替えが難しくなる |
- 建設業や物流業における現場管理
- 医療・介護業界における多業種連携
- 運送業におけるルート最適化や配達実績の管理
- 工場の原価計算や部材管理
- 点検スケジュールやチェックリストの可視化 など
業界特化型の支援ツールは、汎用ツールでは対応できない課題を解決してくれるものです。そのため、まずはノーコード・ローコードツールなどで脱エクセルを目指し、どうしても難しい場合に業界特化型の支援ツールを検討してみましょう。
脱エクセルに成功した企業事例
脱エクセルに適したアプローチは、企業が抱えている課題や目的によって変わります。同じツールを使う場合でも複数の選択肢があるため、実際の事例を見ながらイメージを固めることが重要です。
ここからは、kintoneで脱エクセルに成功した3つの事例をご紹介します。
事例1.脱エクセルで調査票の回収スピードが2倍に/ジヤトコ株式会社
Excelで作成していた企業調査票を、kintoneとFormBridge(フォームブリッジ)で自動集計できるようにした事例です。FormBridgeで回答用のフォームを用意し、その内容がkintone上のアプリに自動蓄積されるシステムを構築しました。
調査票の回収スピードは2倍にアップし、約1人月分の工数削減を実現しています。
参考:サイボウズ株式会社「ジヤトコ – kintone(キントーン)導入実績30,000社 – 導入事例 | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
Web上のフォームとkintoneを連携したい方には、当社の「クライゼル(kreisel)」もおすすめです。
クライゼルは、CRM活動に必要な機能をパッケージ化したツールで、高機能なWebフォームを作成できます。kintoneと連携をすれば、特定の顧客だけにメール配信や会員サイトを提供できるため、マーケティングの効率化にも役立ちます。
2025年3月には、kintoneとの相互連携をサポートする「kreisel Webhook クリエイター for kintone」と「kreisel コネクター」をリリースしました。本サービスを活用すると、非IT部門でも簡単な操作でAPI連携を実現できます。
クラウド型CRMプラットフォーム クライゼル| フォーム作成・メール配信・顧客管理
事例2.日報アプリで店舗間の相互サポートを実現/中山靴店
各店舗の売上をExcelで管理していたところ、「同時編集ができない」「データを上書きされた」などの問題が多発。データの修復ができないトラブルも生じたため、リアルタイム性が高いkintoneで日報アプリを制作しました。
当初は活用が進まない状況でしたが、ハンズオンセミナーなどでkintoneの有意性を伝えると、徐々にデータが集まり始めます。浸透が進むにつれて情報共有もスムーズになり、受注状況に応じて店舗間でサポートし合う体制が構築されました。
参考:サイボウズ株式会社「中山靴店 – kintone(キントーン)導入実績30,000社 – 導入事例 | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
日報アプリにはさまざまな活用方法があり、たとえば顧客管理アプリとルックアップ機能で紐づけると、日報から顧客リストを自動作成することが可能です。そのほか、売上データを日報から集計したり、各種データを工数管理に活用したりする使い方もあります。
事例3.大量のグラフで経営状態を把握/元気でんき株式会社
新規顧客の管理にkintoneを活用し、有用性を理解してから経営分析にまで活用した事例です。当初は別のシステム(Access)で脱エクセルを図りましたが、グラフ作成の負担が大きかったことからkintoneの導入を決断しました。
コールセンターの管理業務にもkintoneを活用しており、Dropboxに保存した録音データのファイルリンクが自動登録される仕組みを構築しています。
参考:サイボウズ株式会社「元気でんき – kintone(キントーン)導入実績30,000社 – 導入事例 | サイボウズの業務改善プラットフォーム」
kintoneで集計したデータは、管理画面から手軽にグラフ化することが可能です。棒グラフや円グラフのほか、折れ線グラフ、クロス集計表なども用意されているため、さまざまな経営データをわかりやすい形で可視化できます。

kintoneは脱エクセルに役立つツールですが、実際の運用で悩みが生じることもあるでしょう。特にあらゆる業務にExcelを活用している場合は、プラグインや外部サービス連携も含めた全体の設計がポイントになります。
スムーズに脱エクセルを実現したい企業には、kintone導入支援・設定代行サービスの利用がおすすめです。当社のサービスではアプリやプラグインの設計に加えて、JavaScriptによるカスタマイズのご提案もしております。
納品後の伴走支援も受けられるので、脱エクセルや業務効率化に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
脱エクセルを実現する4ステップ
代替ツールを導入しても、Excelの問題がすべて解消されるとは限りません。脱エクセルを成功させるには、以下の手順でシステム全体の設計を考えることが必要です。
- 手順1.Excel業務の洗い出し
- 手順2.課題の特定
- 手順3.脱エクセルの必要性や効果の検証
- 手順4.代替ツールの選定
ここからは各手順に分けて、脱エクセルを成功させるポイントを解説します。
1.Excel業務の洗い出し
急にデータが破損するなど、Excel業務のリスクは唐突に訪れることがあります。潜在的なリスクにも対処するために、まずは社内で行っているすべてのExcel業務を洗い出しましょう。
社員データと勤怠データの管理など、ひとつのファイルで複数のタスクをこなしている場合は、業務フローも精査しておきます。「誰が(どの部署が)」「どのタスクに」「いつ」「どうやってExcelを活用しているのか」の観点から、社内のExcel業務を整理してみてください。
2.課題の特定
次は、それぞれのExcel業務が抱えている課題を特定します。「表示速度が遅い」「マクロが複雑化している」などの顕在化している課題に加えて、将来起こり得るリスク(データの破損など)もまとめておきましょう。
たとえば、勤怠管理業務では「担当者しか仕組みを理解できていない」「すぐに引き継げない」などの課題が考えられます。そのほか、最新版のファイルがわからない、気づかないうちにデータが消失するなどもありがちな課題です。
特に潜在的な課題は特定が難しいため、無理をせず専門家に頼ることも考えましょう。kintone導入支援・設定代行サービスを提供している当社は、お客様へのヒアリングを通して最適なソリューションをご提案しております。
3.脱エクセルの必要性や効果の検証
代替ツールで脱エクセルを図ると、基本的には追加コストがかかります。また、業務フローや運用ルールを調整する必要があるため、上層部や上司を説得する意味でも、代替ツールの効果検証は欠かせません。
そのため、各ツールの活用方法を具体的にイメージしながら、事前に「解決できる課題」と「期待できる効果」を明確にしましょう。効果検証の方法はさまざまですが、たとえば以下のような計算式を用いると、追加コストとの比較がしやすくなります。
1日あたりの削減効果(円)= 削減時間(時間) × 対象人数 × 人時単価(円)
削減効果:Excelでの作業と比較して、1人あたりどれだけの時間を削減できたか(1日単位)
対象人数:対象の業務を行っていた人数
人時単価:1時間あたりの人件費
なお、代替ツールがすぐに浸透するとは限らないため、教育コストなども含めた効果検証が必要です。現場にもヒアリングをしながら、脱エクセルの必要性を慎重に判断しましょう。
4.代替ツールの選定
Excelの代替ツールを選ぶ際には、課題やリスクを解決できるかに加えて、以下のポイントを意識します。
- 導入範囲の拡大も見据えて、必要な機能を満たしているか
- プラグインや外部サービスとの連携で、どのようなシステムを構築できるか
- 現場が使いやすいか、マルチデバイスに対応しているか
- 小さな悩みや課題に合わせて、柔軟なカスタマイズができるか
- セキュリティ対策が万全か
前述のとおり、代替ツールには複数の選択肢があり、サービスによっても特性は変わります。具体的な活用をイメージしながら、最も費用対効果が高いツールを選びましょう。
限界を感じる前に脱エクセルを考えよう
Excelは便利なツールですが、無理に使い続けると属人化が進み、対象業務がブラックボックス化してしまいます。ファイルの破損リスクもあるため、限界を感じる前に脱エクセルを検討してください。
ただし、代替ツールの導入前には、入念なシミュレーションと効果検証が必要です。脱エクセルが不要な業務もあるため、一つひとつのタスクを丁寧に精査しましょう。